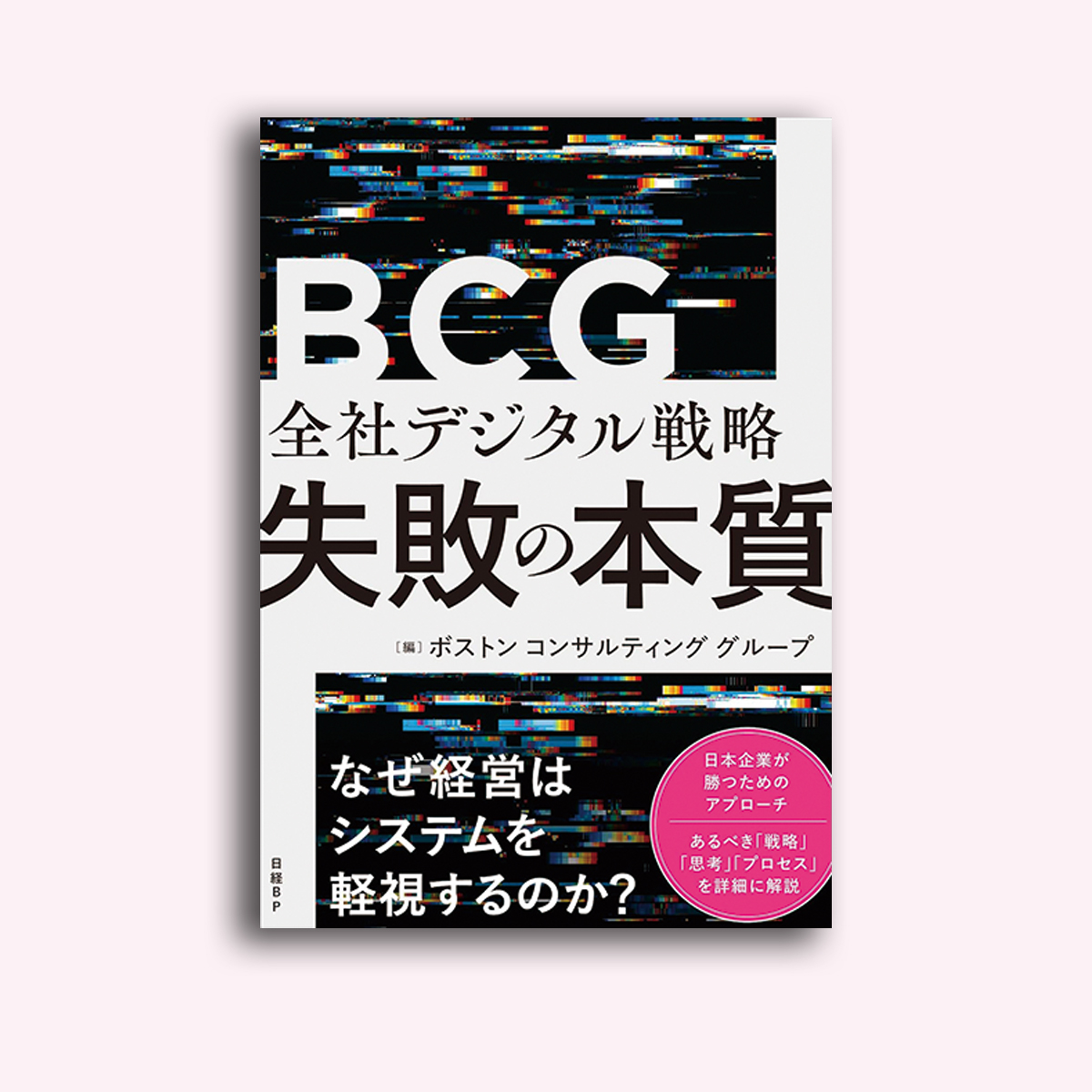『問いの技法─明晰な思考と円滑なコミュニケーションのために』
「正解がない時代」と言われて久しい。では、何を武器にビジネスの荒波を渡るのか。その鍵は問いを立てる力にある。この分野には既に多くの類書がある。だが、本書の際立った特徴は、「問い」とは何かをはっきりさせ、多様な問いを分類・整理して、それぞれの特徴を明らかにしようとする「問いの理論」に基づいている点だ。
この理論を身につけるメリットの1つは、「暗黙の問い」を見出だせるようになることだと著者は言う。私たちは日々の生活の中で、非常に多くの問いを立て、それに答えているのだが、そうした問いの多くは、はっきりと意識されていない。会話の場においては、言葉として表現されないことさえ多いという。
例えば自己紹介。初対面の人には誰しも、自然に自分の名前や所属組織を名乗ることがあるだろう。そこには、「あなたは誰ですか?」という言葉にならない問いが隠れている。聞かれる前から自己紹介するのは、「問いを先取り」しているからだと言える。
私たちのコミュニケーションの大部分は、問いと答えで成り立っているという本書の考え方に基づけば、会話が噛み合わなかったり誤解が生じたりするのは、問いを正しく認識できないためだ。言語化されていない問いを見つけ出し、しっかり意識することが、より良い思考やコミュニケーションにとって極めて有効だと著者は述べる。
相手の問いをキャッチするだけでなく、自ら適切な問いを立てることも重要だ。だが、その重要性を感じている人は意外と少ない。情報が溢れる現代社会では、自分の問いさえ意識されにくい。何かを知りたいと思ったとき、ネット検索で瞬時にそれらしい情報を得ることができる。だが、キーワード検索は問いを曖昧にしてしまう。さらに、ネットサービスにおけるレコメンド機能は、ユーザーの関心がありそうな情報を次々と表示してくる。私たちはますます自分の問いを意識しなくなり、自分が何を知りたいのかを曖昧なままにしてしまう。
情報社会のなかで、自分が「主人」であり続けるために、つまり主体的かつ能動的に生きるためには、自分自身の問いを持つことが必要だ。こうした考え方に基づき本書は、問いを理解して実践的な問いを立てる技法、さらに他者に質問する技術について、豊富な事例を挙げながら詳述している。
最後の補章では生成AIの問題が取り上げられる。プロンプトを入力すれば流暢な日本語で様々な答えを示してくれるが、AIは「本当に」問いに答えているのだろうか。問いに答えているように見えるだけではないのか。著者はそう投げかける。それらしい答えがいとも簡単に生成できるようになったAI時代の今、本書が示す「問いの理論」は、誰もが身につけるべき必須の情報リテラシーと言えそうだ。
『問いの技法─明晰な思考と円滑なコミュニケーションのために』
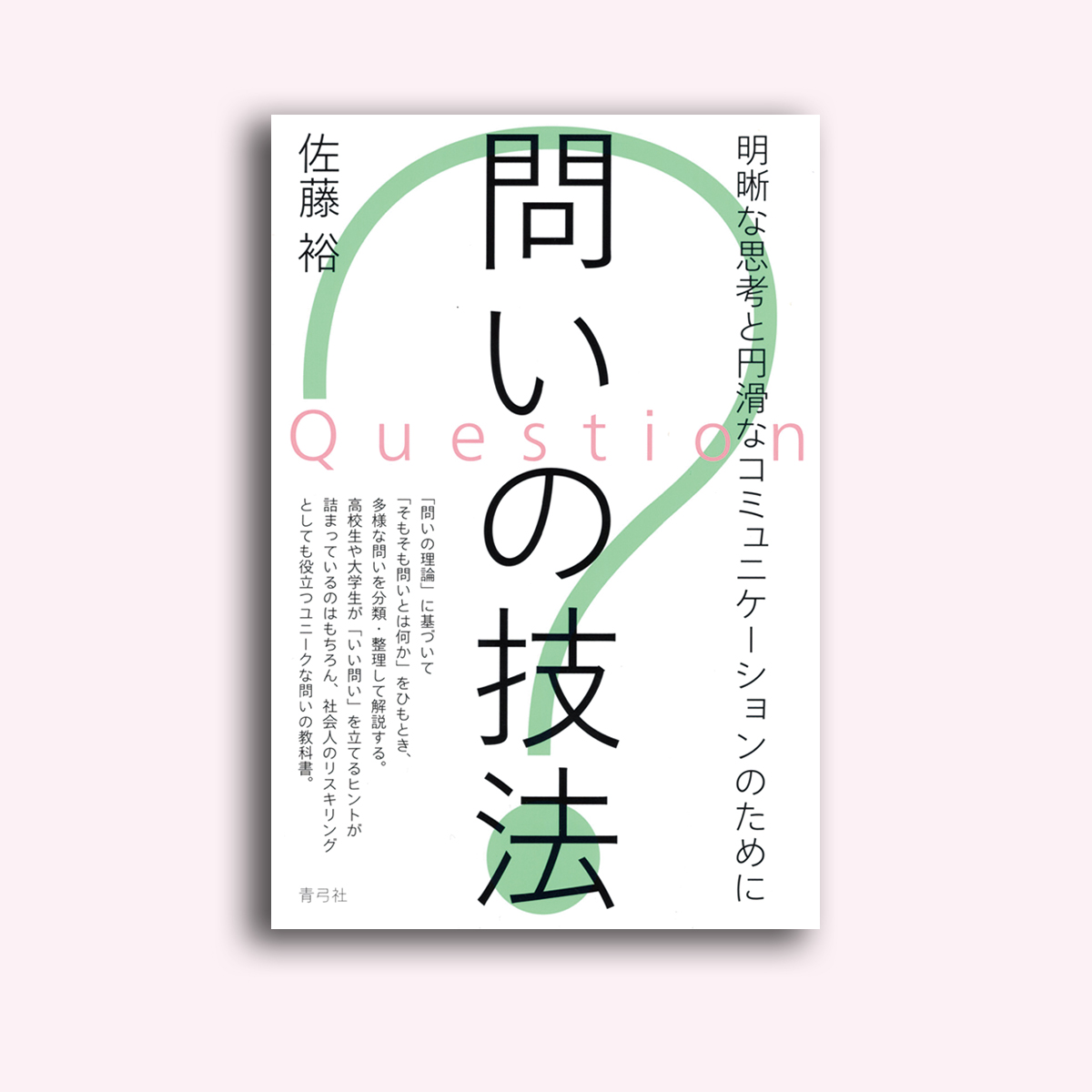
- 佐藤 裕 著
- 本体2,400円+税
- 青弓社
- 2025年5月
今月の注目の3冊
between us
私たちはAIと、創造性を問い直す
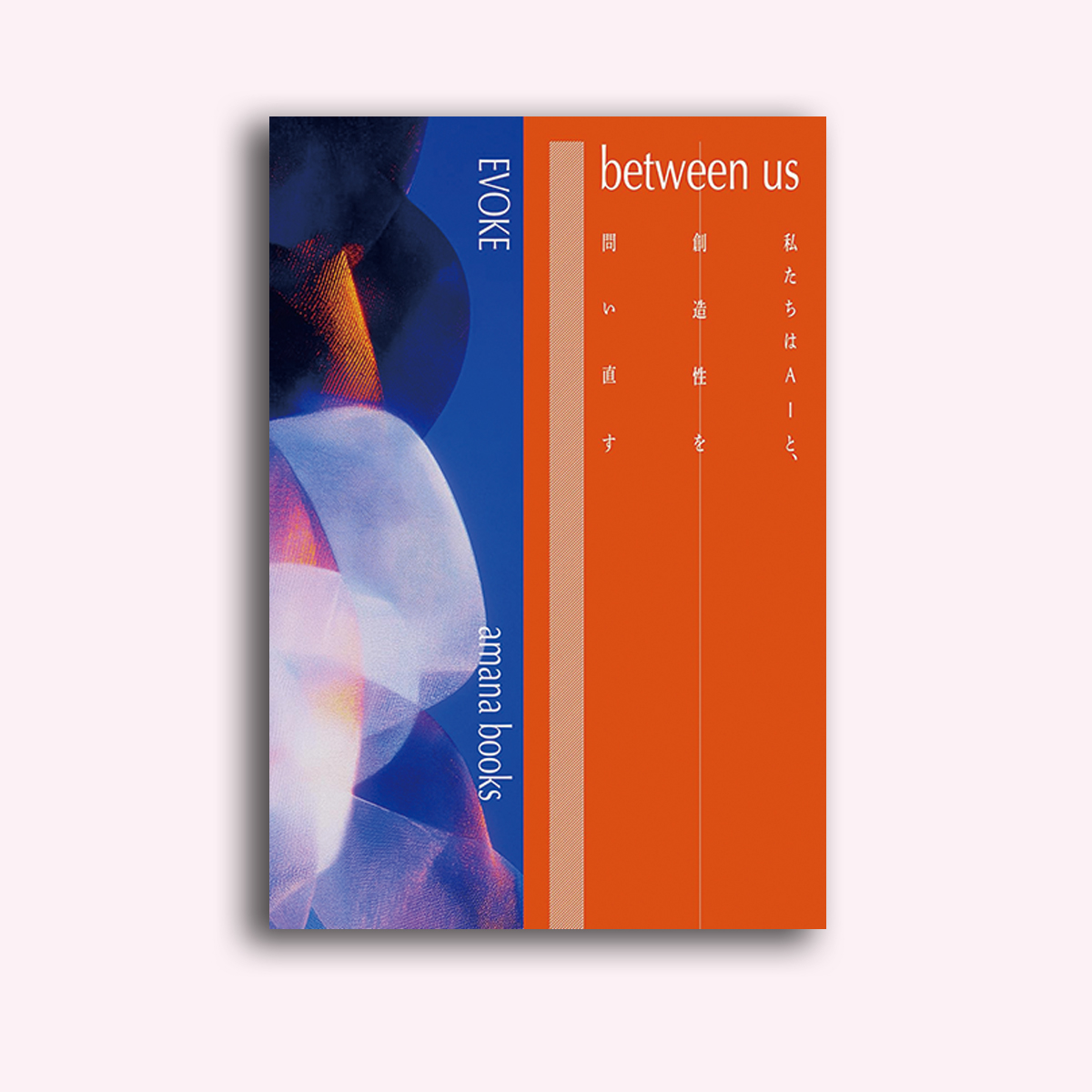
- EVOKE、丸岡 和世、堀口 高士、他著
- アマナ
- 本体2,200円+税
AIに任せるべきことと人間にしかできないことを切り分けよう。よく耳にする議論だが、明確に分けるのではなく、曖昧に揺らぐ「あいだ」に目を向けるとどうなるか。境界の内でも外でもない場所にこそ、創造の余白が潜んでいるのではないか。こうした課題意識から生まれたのが、広告ビジュアル制作業界最大手のアマナ社内クリエイティブチーム「EVOKE」による本書だ。
フォトグラファー、書店店主、歌人、理工学博士など多様なクリエイターや研究者、クライアント企業との対話を通して、様々な角度から創造性の本質に迫る。本書は、生成AIの普及初期からその可能性と向き合い、現場での実践と共有を重ねてきたEVOKEの取り組みをまとめた、1つの通過点であり成果の記録だ。
本書とともに、「AIと人間のあいだ」で揺らぐ創造性について考えてみたい。
ジブリの戦後
国民的スタジオの軌跡と想像力
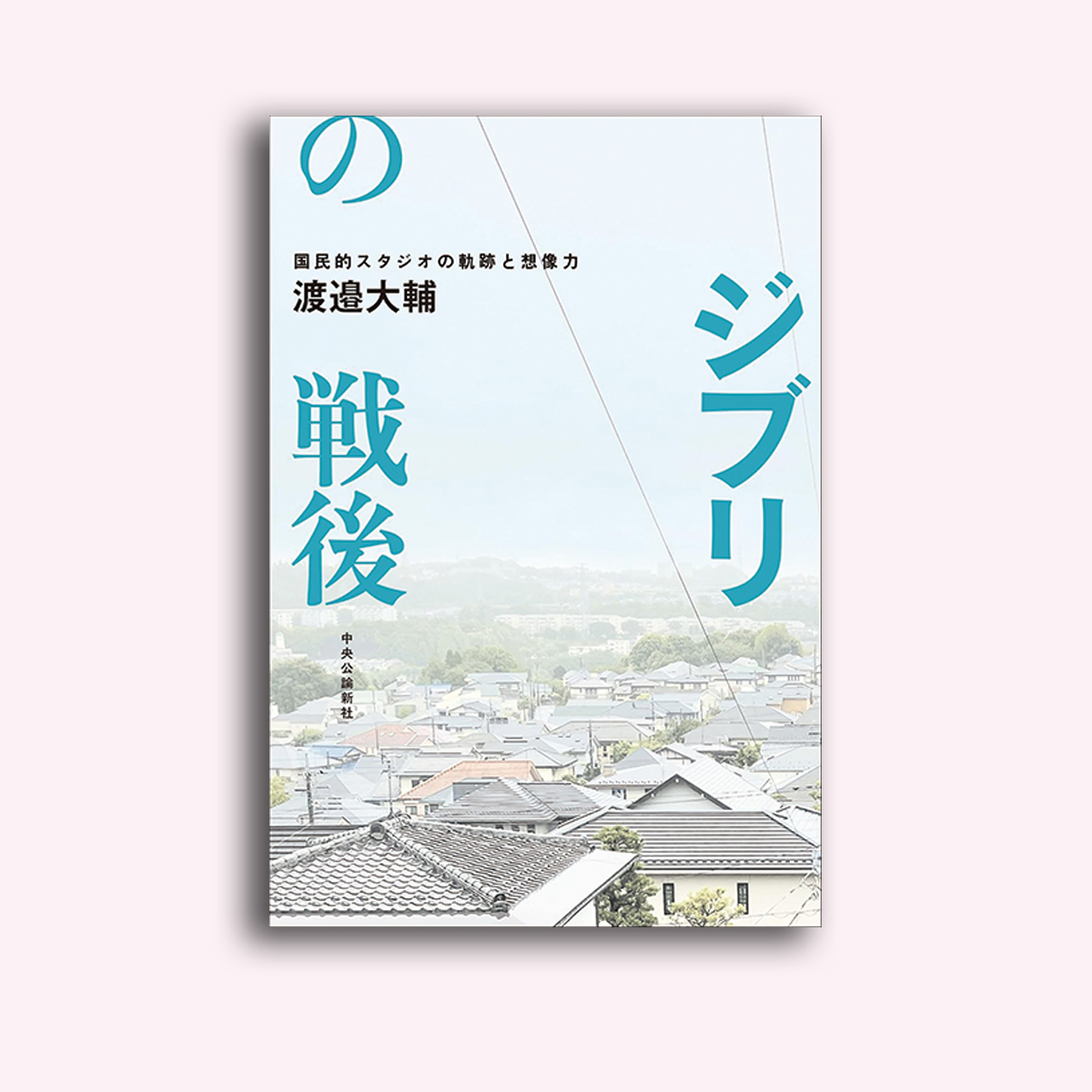
- 渡邉 大輔 著
- 中央公論新社
- 本体2,100円+税
『風の谷のナウシカ』『千と千尋の神隠し』など、世界中で高く評価される作品を制作するスタジオジブリは今年、設立40周年を迎えた。戦後のちょうど半分の歴史を持つことになる。本書は、このスタジオジブリについて、日本の近現代史と重なる「戦後」というテーマから、その歩みと魅力を解き明かす意欲作だ。
ジブリ関連の文献は出尽くした感もあるが、本書の特徴の1つは、宮崎駿や高畑勲などの主要人物だけでなく、「ジブリ」というスタジオそのものを文化的な運動体として総体的に論じている点にある。メディアや思想におけるホットなキーワードとの関係から、現代社会や文化の切り口でジブリを捉え直している点も目新しい。
この稀有な国民的スタジオの軌跡からは、80年をかけて変容してきた戦後日本社会の様々な問題が読み取れる。ユニークな「戦後史」としても興味深い。
全社デジタル戦略
- ボストン コンサルティング グループ 編
- 日経BP
- 本体2,700円+税
日本企業のシステム投資は実に生産性が低い。欧米企業の3倍の工数がかかるという非効率さである。本書は単なる技術論ではなく、経営と組織の問題に切り込みながら、日本企業がIT・デジタル投資で繰り返す失敗の本質に迫る。
システム開発が迷走する背景にあるのは、経営層の無関心や丸投げ体質、マインドセットの欠如だと著者は指摘する。ITは経営戦略そのものであるとの自覚が求められるというのだ。
本書では、プロジェクトの各フェーズにおける失敗の構造を具体的に分析、回避のポイントを丁寧に整理している。業界全体や国レベルでの対応の必要性にも言及し、企業単体では解決し得ない課題への向き合い方も示唆する。
危機意識を高め、多くの企業が改善に向かって動くことで、実質的な危機に直面するのを避けてほしい。そうした意図に貫かれた優れた実務書となっている。
全文をご覧いただくには有料プランへのご登録が必要です。
-
記事本文残り0%
月刊「事業構想」購読会員登録で
全てご覧いただくことができます。
今すぐ無料トライアルに登録しよう!
初月無料トライアル!
- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け
- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題
- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待
※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

 広告掲載のご案内
広告掲載のご案内