世界市場を切り拓いた技術と地域の底力──エヌ・ピー・シーが描く"事業進化の構想"

太陽電池産業の黎明期から世界トップメーカーとの取引を築き、グローバル市場で存在感を発揮してきた株式会社エヌ・ピー・シー。一方で、急速な市場変化や買収失敗により経営危機に直面し、組織の再生を迫られた時期もあった。しかし伊藤雅文社長は、自らの原点である「ものづくり」と向き合い、会社を“普通の、まっとうな組織”へと建て直す改革を進めてきた。愛媛の地域に根差した製造拠点、次世代太陽電池やパネルリサイクル技術の確立など、新たな成長の柱も育ちつつある。世界市場を開拓し、危機を乗り越え、再び未来を描く──その軌跡と構想を追う。
負債からの創業──“ものづくりへ戻る”決断
エヌ・ピー・シーの創業は1992年にさかのぼる。伊藤社長は機械工学の出身で、当初は複数の大手メーカーへの推薦も得られる状況にあったが、「ものづくりをしたい」という思いが揺らぐことはなかった。選んだ道は商社勤務。しかし勤務先がイトマン事件に巻き込まれたことを契機に、「やはり自分はものづくりに戻るべきだ」と考えたという。
当時引き受けたのは、負債を抱え経営が傾いた小さな町工場の技術と事業。その負債を“丸ごと引き継ぐ”形でエヌ・ピー・シーを設立し、スタート時から約2億円の借金を背負った。従業員20名規模の小さな組織で、手元に残る利益のほとんどが返済に消えていく日々だったが、この逆境が伊藤社長の経営観と覚悟を形づくった。
「大変でしたが、あの経験が経営の基礎になりました。派手な成長ではなく、地に足のついた経営をする。この会社をまともな会社に戻すという意思の源泉です」
太陽電池産業の黎明期──世界市場への挑戦
創業当初の主力事業は真空装置だったが、太陽電池の研究用途での引き合いが増え、1990年代半ばには太陽電池(太陽光パネル)製造装置の開発に本格参入した。当時、太陽電池はまだ量産体制すら整っていない段階だったが、伊藤社長は当時最大の市場だった「アメリカ市場への直販」という思い切った戦略に出た。
普通なら商社を介すところ、自社で直接交渉し、世界最大規模のメーカーから評価を獲得。1996年進出から1年後には米国での事業が軌道に乗り、続く欧州でもドイツのFIT政策(固定価格買取制度)と重なり市場が急速に拡大した。こうしてエヌ・ピー・シーは世界市場の中で実績を積み上げていった。
「当時はベンチャー的な勢いもあった。とにかくまずは動いてみる。それが世界市場を開く力になったと思います」
急成長と“危機”──市場崩壊と買収失敗、組織の再生へ
しかし、2000年代後半になると状況は一転する。中国メーカーが大量に参入し、太陽電池市場は過剰生産と価格破壊に陥った。さらに競合メーカーの買収も裏目に出て、エヌ・ピー・シー自身が経営危機に追い込まれた。
650名規模に膨らんだ組織は、拠点閉鎖と人員整理を迫られる。伊藤社長は就任後、各国の拠点を回って解散や縮小の説明を行い、世界中で広げた事業を自らの手で畳んでいった。
「逃げずにやらなければいけないことがある。辛い経験でしたが、ここで価値観が大きく変わりました。自分たちが“普通の会社”になるために、根本から組織を見直す必要があった」
制度改革、人事制度の刷新、退職金制度の導入など、会社の“土台”を整えることに向き合った。
「地域の底力」とともに──愛媛が支えたものづくりの再構築
エヌ・ピー・シーの主要製造拠点は愛媛県松山市にある。150名以上の技術者が働き、地場の真面目で誠実な人材が高い品質を支えている。
しかし地方採用は年々難しくなっており、大手企業の採用強化による競争も背景にある。そこで伊藤社長が着手したのが、地域との接点を増やすための“植物工場ビジネス”である。工場屋上に設置したリユースパネルで発電した電気を用い、レタスをLEDの人工光で栽培し、「はこひめレタス」として地元で販売。消費者に身近な形で企業を理解してもらう狙いがあった。
「機械ばかりでは地元に何をしている会社か伝わりにくい。地域に開かれた存在になりたかったのです」
レタス工場は、地域と企業が連携しながら歩む象徴的な取り組みになっている。
次の成長の柱──太陽電池の未来とリサイクル、そして産廃市場へ
近年、エヌ・ピー・シーは太陽電池産業の“次の波”に向けた事業を着実に進めている。
そのひとつが、軽量で低コスト化が期待される次世代太陽電池ペロブスカイトの領域だ。韓国の先端企業やアメリカ、国内メーカーなどと連携しながら、装置メーカーとしての知見を生かした新技術開発に挑んでいる。まだ市場は見通しきれない部分も多いが、「今のうちから技術を持つことが大切」と伊藤社長は語る。
さらに大きな柱となりつつあるのが、太陽光パネルのリサイクル事業である。熱したナイフでパネルのガラスと金属を含む素材を分離する独自技術「ホットナイフ分離法🄬」によってガラスを分離後、さらに新技術であるブラシかきとり法で処理したガラスがAGC(旧旭硝子)の評価のもと“水平リサイクル(同品質の製品への再生)可能”と認められた。2014年から開発を続けてきた技術が、10年越しの実績として実を結んだのだ。
「パネル廃棄が2035年頃にピークを迎えると言われています。その前に、国内外でリサイクルの基盤を整えていくことが不可欠です。装置メーカーとして、我々ができることはまだまだあります」
そして三つ目の柱として、産廃業界へのアプローチも進む。太陽電池パネルの処理はもちろん、その他廃棄物の選別工程でも同社の機械技術は応用可能であり、実際に複数の地域企業との取り組みが始まっている。
日本国内はオーナー企業が多く、意思決定が早いことから、事業展開のスピード感も期待できる領域だという。
本質を捉え、行動する──未来の経営を担う人へのメッセージ
エヌ・ピー・シーの歩みには、伊藤社長の一貫した姿勢が表れている。それは、「ものごとの本質を捉え、行動を恐れない」という姿勢だ。
アメリカ進出も、ペロブスカイトへの挑戦も、植物工場ビジネスも、すべては“兆しを捉え、まずやってみる”という行動から始まった。逆に、買収失敗の経験は「正しい判断は常にできない」という教訓となり、その後の経営改革の原動力にもなった。
「全部が正しい判断とはいきません。ただ、“何が正しいのか”を考え続ける姿勢が大事です。本質を捉えることができれば、チャンスを逃さない。事業を進化させる力になります」
危機を越え、地域とともに再生し、再び世界へ挑むエヌ・ピー・シー。 その姿は、中堅・中小製造業が未来へ活路を切り開くための大きな示唆に富んでいる。
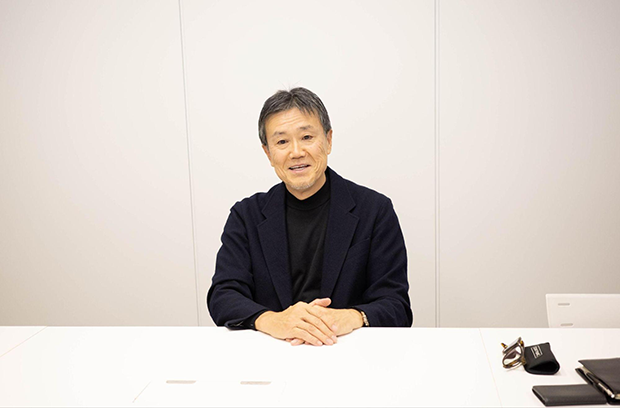

 広告掲載のご案内
広告掲載のご案内