『世界は知財でできている』 AI時代の「教養としての知財」
AIが文章や画像、音楽を自在に生み出す時代になり、私たちはこれまでとは全く異なる世界に生きている。SNSやネット上には生成AIによるコンテンツがあふれ、もはや人間の創作と見分けがつかないほどだ。だからこそ、「AIが作った作品に著作権はあるのか」「学習のために他人のデータを自由に使ってよいのか」といった疑問が湧いてくる。AIが過去の創作物を「元ネタ」として学ぶ以上、人間の「知的財産(知財)」をどう扱うかは避けて通れない問題である。
「知財」とは、人間の知的活動によって生まれた情報や創作物のうち、財産的価値を持つものを指し、それを保護する権利が「知的財産権」である。音楽や文章、デザインだけでなく、スマホや家具、街の建築やモニュメントなど、日常のあらゆる場面に知財は息づいている。本書は、こうした知財の基本から最新動向までを、専門外の読者にもわかりやすく解き明かす。AI、商標、著作権、特許、国際問題など幅広いトピックを扱い、「知財リテラシー」をアップデートすることを目的としている。
生成AIの登場は知財の常識を大きく揺さぶっている。感情や思想のないAIは「著作者」になれず、生成AIによる画像や音楽には著作権が認められないことが多い。だが中国では2023年、AI画像の投稿者に著作権を認める判決が出るなど、対応は揺れている。技術革新にルールが追いつかず、各国が模索を続けているのが現状だ。
2知財は研究やビジネスの競争力にも直結する。ユニクロのセルフレジ技術をめぐり、ITベンチャー・アスタリスクが訴訟を起こした例は記憶に新しい。和解が成立したが、大企業を相手にスタートアップが特許権を武器に渡り合ったこの事件は、知財が「弱者の防具」となり得ることを示した。
農業でも知財問題は深刻だ。日本開発の高級ぶどう「シャインマスカット」は種苗が海外に流出し、中国や韓国、東南アジアで大量に栽培されている。日本の損失は年間100億円超とされるが、あいにく現行制度では防ぎきれない。国際的なルール整備と知財意識の強化が急務である。
こうした事例から見えてくるのは、知財がもはや専門家や企業法務だけの話ではないという現実だ。SNSで発信する個人、AIを使うクリエイター、商品を企画するビジネスパーソンなど、誰もが知財の担い手であり、加害者にも被害者にもなり得る。他人の権利を尊重しつつ自分の成果を守る知恵が求められている。
本書は法的専門用語をかみ砕き、日常に引き寄せて語ることで、読者が自分のこととして理解できるよう工夫されている。知財を単なる法律知識でなく、現代を生き抜く教養として捉え、学んでいくための第一歩を踏み出すガイドとなるだろう。
『世界は知財でできている』
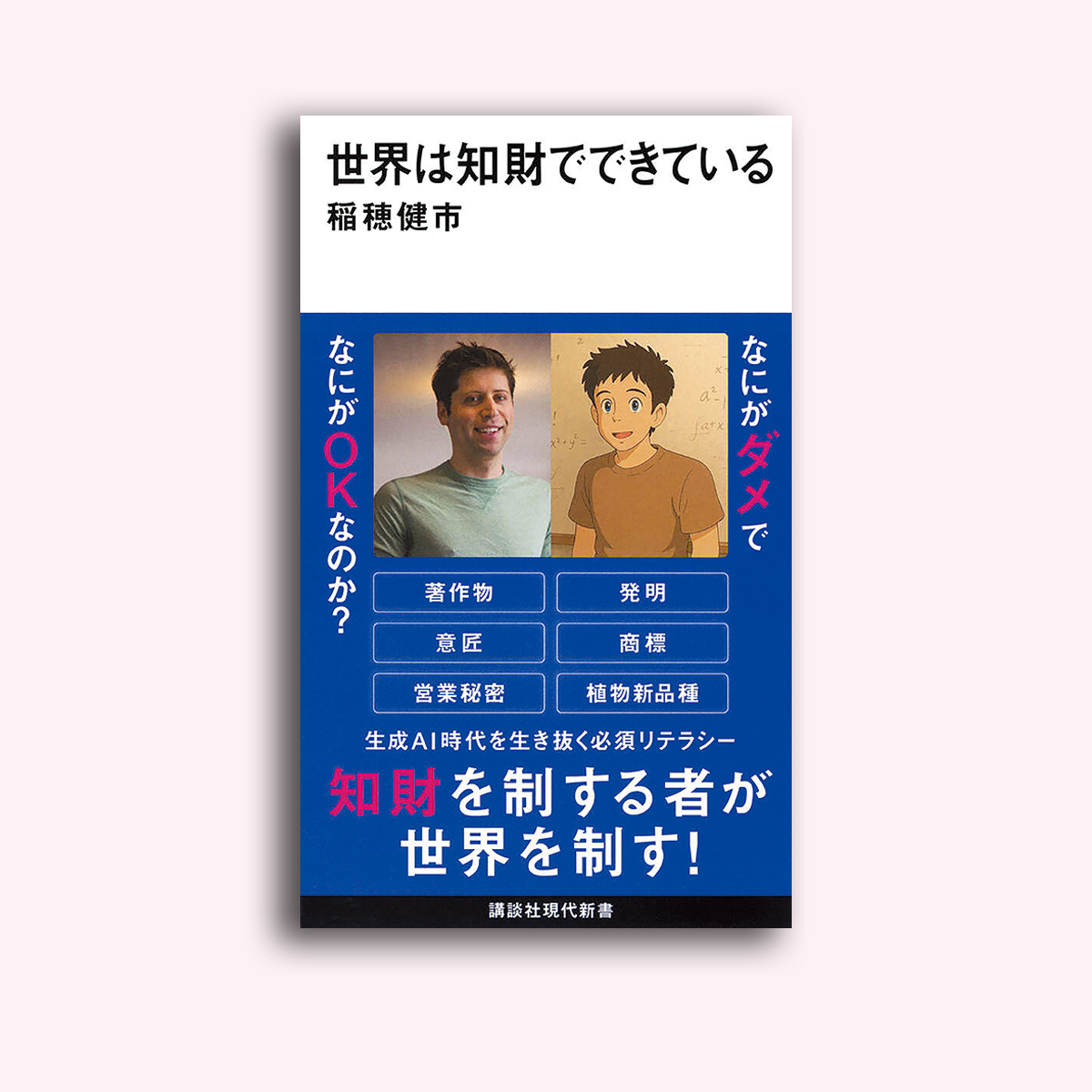
- 稲穂 健市 著
- 本体1,100円+税
- 講談社
- 2025年8
今月の注目の3冊
資本主義にとって
倫理とは何か
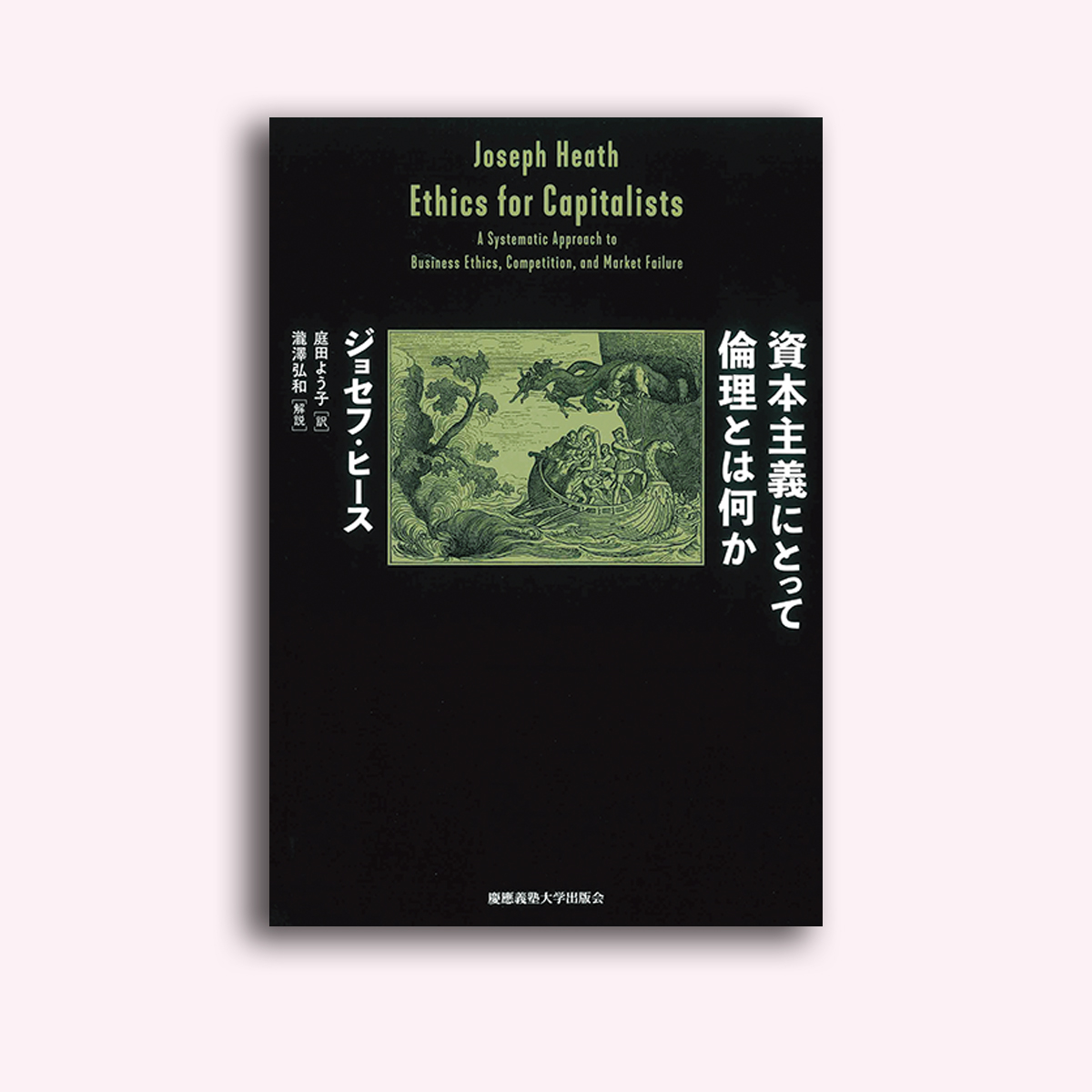
- ジョセフ・ヒース 著、庭田 よう子 訳
- 慶應義塾大学出版会
- 本体3,200円+税
競争が無駄を淘汰し、イノベーションが市場を活性化させる。資本主義は企業の創意を最大限に活かす極めて効率的な仕組みだ。個人としてもその恩恵を受けていない人はいないだろう。だが同時に、格差拡大や貧困、倫理の形骸化を招くとして批判されることも多い。利益を最優先する論理が、人間や社会の豊かさと衝突するためだ。
市場経済の効率性と倫理的正当性の間にある緊張関係を正面から捉え、市場や企業、個人の行動規範をどう構想すべきかを体系的に論じているのが本書だ。
カナダの哲学者ジョセフ・ヒースは、学術書と一般書の双方で多数の著作を発表しており、『啓蒙思想2.0〔新版〕─政治・経済・生活を正気に戻すために』など日本語訳されたものも多い。独自の視点から長年議論してきた「ビジネス倫理」にまつわる壮大なヴィジョンが展開される本書は、読み応えのある骨太の意欲作である。
通史で読み解く自動車の未来
大局を見渡し、戦略を導く
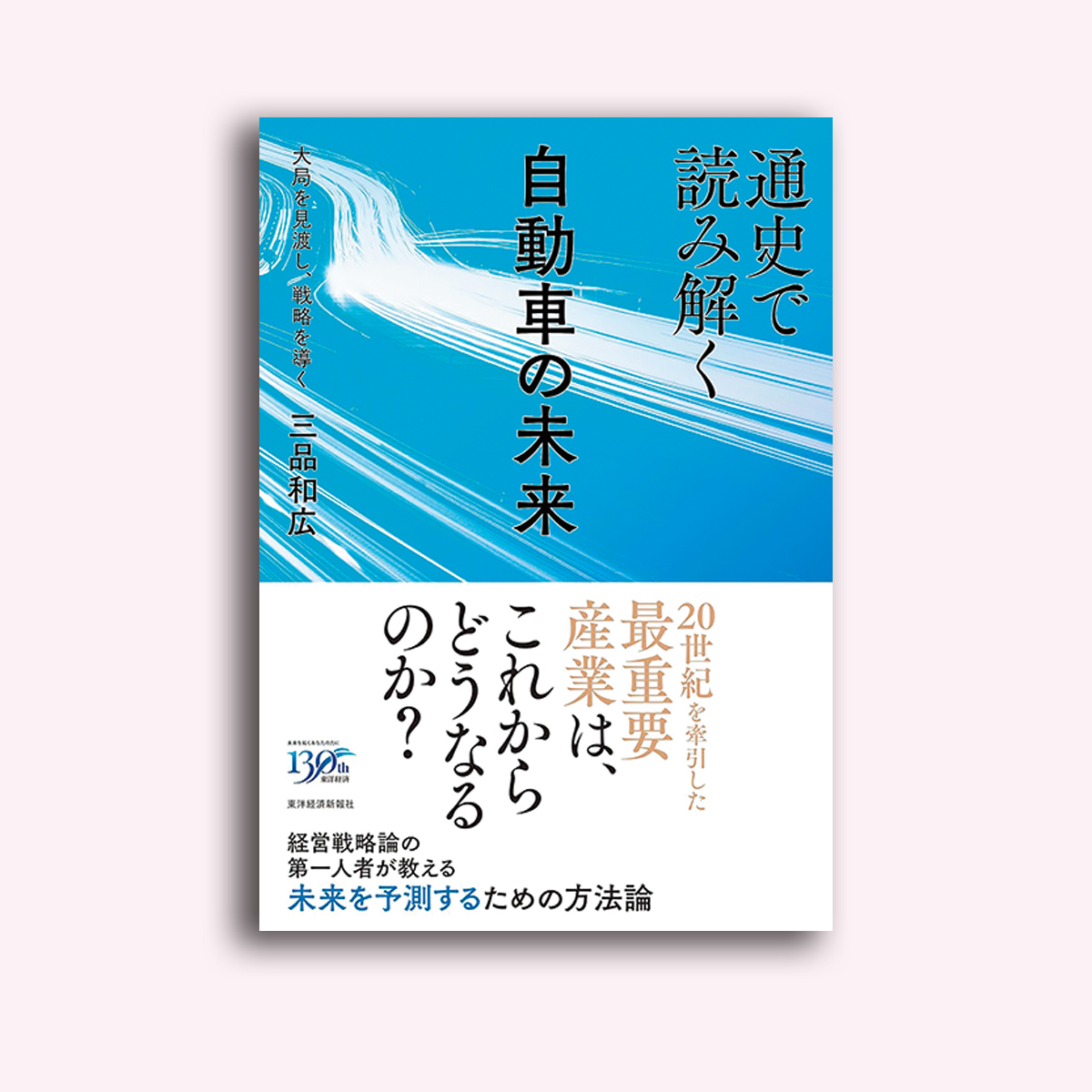
- 三品 和広 著
- 東洋経済新報社
- 本体2,200円+税
自動車産業は今、100年に1度の変革期にある。そう喧伝されるが、こうした「津波」に惑わされてはいけないと著者は説く。ここでいう津波とは、農業革命、産業革命、情報革命といった、社会を隅から隅まで洗う大変化のことだ。
著者が積み上げてきた600余のケーススタディを踏まえれば、ビジネスにおける戦略機会を提供するのは、常に局所的な変化だという。背景に「大波」があるとしても、複数の業界だけを襲う「中波」や特定の業界にだけ影響する「小波」、さらに襲われたほうも気づかないような「さざ波」にこそチャンスが潜んでいる。
小さな波でも、いち早く捉えることが肝心だ。そのために本書は自動車産業の歴史を時系列に3部9章で構成し、業界の通史を概観する。終章ではシビアな未来予測も展開される。一社でも多くの企業が難局を好機に転じてほしい。著者の願いが込もった一冊だ。
お土産の文化人類学
地域性と真正性をめぐって
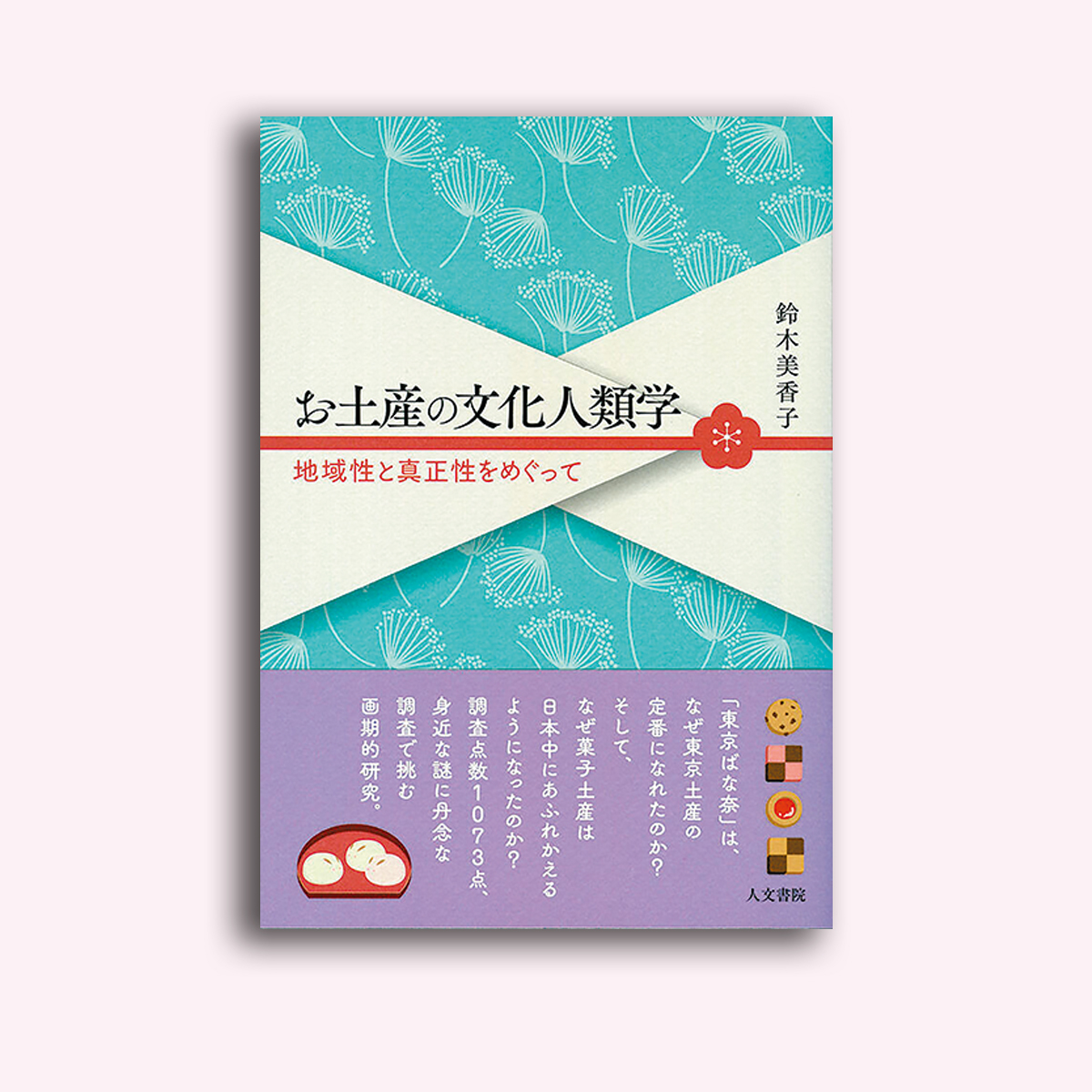
- 鈴木 美香子 著
- 人文書院
- 本体2,400円+税
旅行に行ったら土産に菓子を買い、同僚や友人に配る。ごく当たり前に思えるが、こうした習慣が広まったのは最近のことらしい。1980年代までは、キーホルダーなどの記念品が旅の土産の定番だった。ところが「東京ばな奈」の大ヒットを経て、1990年代以降は菓子土産が一気に広まる。
菓子製造機器メーカーを中心に、企画・製造・販売を一貫してサポートする体制を構築。工場を持たない事業者の参入も促進した。馴染みの菓子も販売場所を限定して地域性を打ち出し、付加価値を獲得。今世紀に入ると、地元の素材を活かした特産品菓子が次々と生まれ、消費者も地域色ある「本物らしさ」を求めるようになった。
本書は1073点に及ぶ調査を基に、菓子土産の誕生から現在に至る変遷を文化人類学的に解き明かす。土産という身近な行為を通じて、日本社会の変化と欲望のあり方が鮮やかに浮かび上がる。
全文をご覧いただくには有料プランへのご登録が必要です。
-
記事本文残り0%
月刊「事業構想」購読会員登録で
全てご覧いただくことができます。
今すぐ無料トライアルに登録しよう!
初月無料トライアル!
- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け
- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題
- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待
※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

 広告掲載のご案内
広告掲載のご案内