AIで医療を変える──エルピクセルが挑む“社会実装型ディープテック”
医療の現場でいま、静かな変革が始まっている。深刻化する放射線科医の人手不足、膨張する医療費、遅々として進まない創薬の効率化──こうした課題に真正面から挑むのが、ライフサイエンス領域に特化したAIスタートアップ・エルピクセル株式会社だ。画像診断支援AI「EIRL(エイル)」、創薬支援AI「IMACEL(イマセル)」という2つの事業を軸に、医療現場への“社会実装”を進める同社。その背後には、支援者から当事者へと転じた代表・鎌田富久氏の「妄想科学的」構想と、深い覚悟があった。
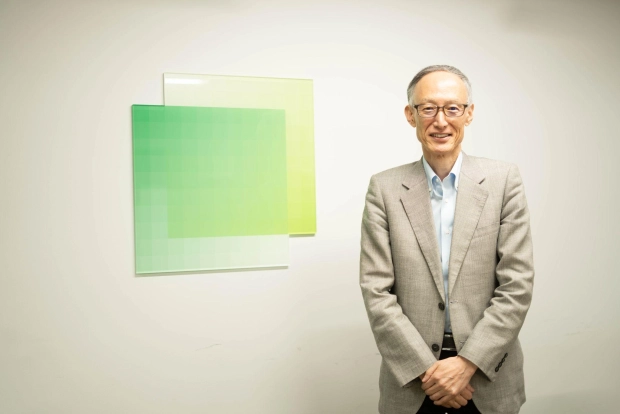
医療の構造課題に挑む、AIの社会実装モデル
エルピクセルの主力製品「EIRL」は、放射線画像の診断支援を行うAIソフトウェアだ。医師の目では見落としかねない微細な病変の検出を画像解析AIによって補完し、診断精度の向上と医療の質を支えている。
「日本は医療画像の撮影件数が非常に多い一方、放射線科医が圧倒的に足りていません。EIRLは、まさにそのギャップを埋める存在です」と語るのは、代表取締役社長CEOの鎌田富久氏。
実際、日本にはおよそ7,000人の放射線科医がいるが、そのうち放射線“診断”専門医に限れば約6,000人。これは人口比で見ても米国の約3分の1にとどまり、過重労働や見落としリスクが医療現場の深刻な課題となっている。
全国約18万の医療施設のうち、EIRLはすでに1,000施設以上(2025年6月時点)に導入されている。まだ1%にも満たないが、診療に“踏み込む”AIとして、医療機器としての厚労省認可も取得し、着実に普及が進んでいる。
一方、「IMACEL」は、創薬の各フェーズにおける画像解析を支援するAIプラットフォームだ。たとえば、研究者が細胞画像などを解析する工程を自動化・高度化し、新薬開発のスピードと成功確率を高める。第一三共との全社的な提携をはじめ、大手製薬企業での実績が積み上がっている。
「私たちは“ソフトウェアで命を救えるかもしれない”領域に取り組んでいます。その技術を社会に届けきることが、今の最大のミッションです」
放射線科医不足だけではない、医療現場の“裏側”
EIRLが開発された背景には、医療現場の“リアルな課題”がある。診断ミスや見落としは、人手不足や過重労働に起因することが多く、放射線科医一人当たりが扱う画像数は年々増加傾向にある。診療報酬制度との関係で、診断に時間をかけることも難しい中、AIが診断を“補完”するというモデルが求められていた。
「EIRLは、従来の“業務支援”ツールとは違い、医師の診断に直接関わる存在です。だからこそ、導入には慎重さが求められますし、私たちもそれを理解した上で社会実装を進めています」
導入後の効果についても、単に“便利なツール”ではなく、「医療の質が向上する」「患者の安心感が増す」といった、より本質的なフィードバックが得られているという。
東南アジアへ──“AI医療インフラ”としての展開
同社の成長は、国内にとどまらない。EIRLは既に東南アジア6カ国へ販売あるいは販売準備を進めており、これからの展開の主軸のひとつとなっている。
「先進国では“AIが医師の仕事を奪う”という議論もありますが、私たちが展開している国々では、そもそも医師が足りていない。AIはむしろ“医療アクセスの格差”を埋める存在として歓迎されているのです」
例えばインドネシアやフィリピンなどでは、人口あたりの医師数が日本の半分以下にとどまり、都市部と地方での医療格差も深刻だ。こうした地域でEIRLのようなAIツールが導入されることで、診断精度と医療水準の底上げが可能となる。
さらに、AIによる診断の効率化は、診療プロセスの無駄を削減し、結果として医療費の適正化にもつながる。日本国内でも、医療費の高騰が長年の社会課題となっている中、EIRLのような“見えない部分の効率化”が果たす役割は大きい。
社会実装を可能にした“未来創造の実験”的カルチャー
医療×AIという最先端領域に挑むエルピクセル。その裏には、型破りともいえる独自の企業文化が息づいている。
「うちは“未来創造の実験場”なんですよ」と鎌田氏は笑う。「理想を描き、未来を創る」というバリューのもと、社員が自由に発想し、新しい技術やアイデアに挑戦できる環境がある。
EIRLやIMACELの開発においても、初期段階からプロトタイピングを重ね、現場からのフィードバックを得ながらブラッシュアップを繰り返してきた。その根底には、「聞きたい声だけを聞かない」「耳の痛いフィードバックにこそ真実がある」という姿勢がある。
「マーケティングやプロダクト設計において、ユーザーの声を正しく聞き取る力が何より重要です。社会実装型スタートアップには、技術だけでなく、“聞く力”が問われます」
医療インフラの一部として、“なくてはならない存在”へ
今後の展望として、エルピクセルは診断支援から治療支援、創薬支援まで、医療の全フェーズにAIを組み込む構想を描いている。
「診断のEIRL、創薬のIMACELだけでなく、オリンパスと連携した手術支援AIの実用化も進んでいます。将来的には、病気になったとき、患者が気づかないうちにエルピクセルのAIがどこかで関わっている──そんな状態を目指しています」
医療DXやデジタルヘルスが叫ばれる中で、エルピクセルは単なるソリューションベンダーではなく、“AI医療インフラ”として、社会に溶け込む存在を目指している。
“支援者”から“当事者”へ──代表就任の舞台裏
こうしたビジョンの裏には、代表・鎌田氏の決断があった。もともとエルピクセルの創業期から関わり、社外取締役や投資家として支援していた鎌田氏は、2020年、経営危機をきっかけに代表に就任した。
「当時、横領事件が発覚し、会社としては危機的な状況でした。でも、ようやくEIRLが薬事承認を取得した直後で、ここで止めるわけにはいかないという想いがありました」
自身も過去にIT企業ACCESSを20年以上経営した経験を持つシリアルアントレプレナー。支援者、起業家、経営者としての複眼的視点を活かし、事業の再構築と社会実装を進めてきた。
「この分野にもっと人が来てほしい」──人材へのメッセージ
「エンジニアや営業・マーケティング人材にとって、医療AIというのは“高度すぎる”と感じるかもしれません。でも、そんなことはありません。大切なのは、社会課題への関心と、自ら学び続ける意志です」
現在、同社のビジネス部門には約20名が在籍し、営業・マーケティングチームの強化が進められている。特に求められているのは、「医療の専門性」と「AI・ソフトウェアの知見」を横断的に理解し、顧客と対話できる“ハイブリッド人材”だ。
「高度な知識を持った営業やPM、エンジニアが活躍できる土壌は整っています。そして何より、ここで得られるやりがいは、どこにも負けません」
人材の流出防止にも力を入れており、インセンティブ設計や評価制度などの整備を進めている。今後はHRの強化も経営課題の一つとして位置づけているという。
終わりに──“医療AI”というフロンティアを共につくる
「これまでソフトウェアは、エンタメや業務効率化の世界で活躍してきました。でも、これからは、人の命や健康に貢献する“責任あるテクノロジー”としての活用が求められます」
そう語る鎌田氏の言葉の裏には、20年以上にわたり起業・経営・支援の現場に立ち続けたリアリティがある。エルピクセルが描く“医療AI社会実装”の未来は、今まさに形になりつつある──。

 広告掲載のご案内
広告掲載のご案内