社会を巻き込む構想力で地域に新たな価値を 新球場建設までの道のり
北海道北広島市に誕生した北海道日本ハムファイターズの球場「エスコンフィールドHOKKAIDO」。球場建設にとどまらず、周囲のまちを含めて官民一体で地域価値を創造した事例となった。いかにして既存の枠組みを超え、「世界がまだ見ぬボールパーク」を実現したのか。その構想と実装の軌跡を聞いた。

鼎談ファシリテーター/松江英夫 社会構想大学院大学 教授、事業構想大学院大学 客員教授
新球場建設の妄想を
構想に変えた3年間の対話
── 「エスコンフィールドHOKKAIDO」が開業して3年目を迎えました。この構想はどのように始まったのでしょうか。
前沢 2004年に北海道日本ハムファイターズが誕生して以来、地元の皆さんにきちんとバリューを提供できているのか、このまま会社が持続できるのかという問題意識を抱えていました。そこで2015年、北海道日本ハムファイターズ取締役の三谷仁志と2人で新球場構想を本格的にスタートさせました。キーワードは「共同創造空間」。スポーツは人数制限がありますが、ビジネスはより自由です。それぞれ強みを持った方々とご一緒して、勝ちに行こうと考えました。

前沢賢 ファイターズ スポーツ&エンターテイメント 常務取締役、北海道日本ハムファイターズ 取締役
川村 初めて前沢さんから構想を聞いたとき、「野球をやってればいいのに、なぜ他の、先のことまで考えるのか」と感じました。しかし行政の立場でも、人口減少の中で目先の対策だけでなく、もっと将来のことを考える必要がある。同じだと思い、共感しました。北広島市には50年以上前から総合運動公園を作ろうとしていた未開発地がありました。行政は「妄想」を掲げにくいのですが、妄想を構想に変えて現実に変えるプロセスを、我々も実践できると思いました。
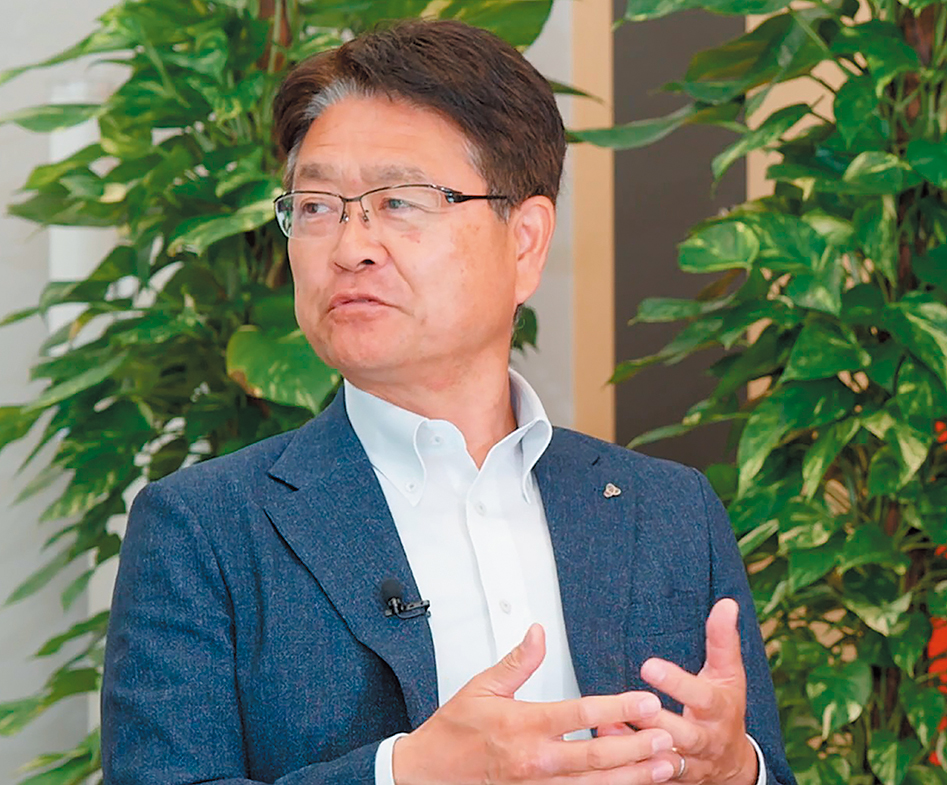
川村裕樹 北広島市 副市長
伊藤 8年前、雑木林だった現地を見、正直データも何もない中で事業判断を下しました。でも前沢さんと三谷さんの言葉の強さ、覚悟、事業にかける思いを聞いて、「ここで決めなければ何のためにデベロッパーをしているんだ」という原点に立ち返りました。この人たちと「世界がまだ見ぬボールパーク」を実現させたい。まちづくりに対する熱意に共感し、その場で一緒にやらせてほしいと申し出ました。

伊藤貴俊 エスコン 代表取締役社長
将来の地域構想を説き
公平性の壁を突破
── 官民連携で最も難しかったポイントは何でしたか。
川村 公平・不公平感をどう説明するかが一番難しかった。「なぜあの企業だけに」という声に対して、50年間野ざらしだった土地に数千人の雇用が生まれ、経済活動が始まると説明しました。正しい情報を責任ある立場から伝えると、最後は強力な味方になってくれる人もいました。「子供たちに未来を見せましょう」と言い続けました。
前沢 親会社の日本ハムから承認を取るのに3年かかりました。本業でないものに何百億円の投資、資料は千ページにのぼります。でも中途半端に進めたら迷惑がかかる。説明責任をきちんと果たしたから、今はとても応援してくれています。
── ルールを変えることも重要だったのでは。
川村 自治体は規則、条例、予算、権限を持っています。今の枠組みに当てはめたらできないことでも、ちょっとした解釈や改正で、法を犯さない限り価値を生むことができる。条例は変えましたし、新しい条例も制定しました。ルールは守るものではなく作るもの。その労力を惜しむか惜しまないかが分かれ目です。
プロジェクト実装の鍵
となるのは「人」の力
── 構想を実装していく上での課題は何でしたか。
前沢 エスコンフィールドは開業3年目で、人間で言えばまだ小学校3年生くらいです。施設の運営は知識もノウハウもゼロからのスタートでしたが、知らないがゆえにできることもあった。お客さんの声に耳を傾けて、柔軟にルールを変えています。開業初日の朝礼で「お客さんの意見だからとか、我々の意見だからとか関係なくやるべきことをやる」と話しました。
伊藤 開業当初、試合後の渋滞でSNSに書き込まれましたが、前沢さんも三谷さんもインカムをつけて交通誘導している。こんな現場のトップがいるでしょうか。施設を開業するだけでなく、オペレーショナルアセットとして最大価値化しているのが北海道日本ハムファイターズであり、インフラ等まちづくりのバックアップをしているのが北広島市です。全く慢心もおごりもなく、さらに良く変えていくために何ができるかを常に考えておられる。我々ももっとこの街の価値を高めるためのアクションを起こせないかと、常々考えている。
川村 開業したら終わりではない。街づくりという原点を忘れないよう、2018年、19年の思いを伝え続けています。人事異動で人が変わっても、普遍的な考え方として継承していく。コアとなる人間をポイントポイントに配置していくことが大事です。
── 次世代のリーダー育成についてはどうお考えですか。
前沢 025年1月に組織を2つに分けました。目前の営業のためには変えない方が良かったかもしれませんが、将来を考えると次の人が育ちにくい体制になっていると思いました。結果的に組織改編で業績は良くなりました。このプロジェクトがここまで受け入れられたのは、8割が運だったと思います。その8割を手繰り寄せたのは、自社、パートナーといった「人の力」です。次世代のリーダーは、運を手繰り寄せられる、つまり、多くの人に能動的に関わってもらえるような土壌をつくることが重要だと思います。
伊藤 リーダー育成にマニュアルはありません。我々が意志を持って取り組む姿勢を見せ続け、共感して同じ夢を実現する意思を持つ者にチャンスを与えていくことに尽きます。
川村 組織として足りない部分を補い合い、方向性を見出す座組みを作ることが大事。ボールパークをきっかけに、6万人弱の町では出会えない企業や人と接点ができた。これも職員への投資だと思っています。
── トライセクターリーダーシップ、つまりパブリック、プライベート、ソーシャルの3つのセクターを超えて協働できる人材が重要ですね。皆さんは社会のために本気でコミットし、ルールを変えることをいとわず、次世代を育てている。まさにそれを実践されています。
前沢 北海道日本ハムファイターズはベンチャー企業のような会社です。大企業、中小企業関係なく、チャレンジしたいと思う方と一緒に仕事をしたい。ぜひエスコンフィールドにお越しいただき、そういう企業さんとご一緒できることを望んでいます。

 広告掲載のご案内
広告掲載のご案内