マテリアルハンドリング技術で 水上ロボットによる河川ごみ回収
物流や生産現場でモノを効率的に動かす「マテリアルハンドリング」技術をコアに、BtoBのソリューション事業を展開してきたダイフクが、社会課題の解決に挑む。河川ごみの回収・調査の実証と今後の見通しについて、ダイフク ビジネスイノベーション本部 担当部長の松田靖氏に聞いた。
聞き手 : 小宮信彦 事業構想大学院大学 特任教授/電通 シニアイノベーションディレクター
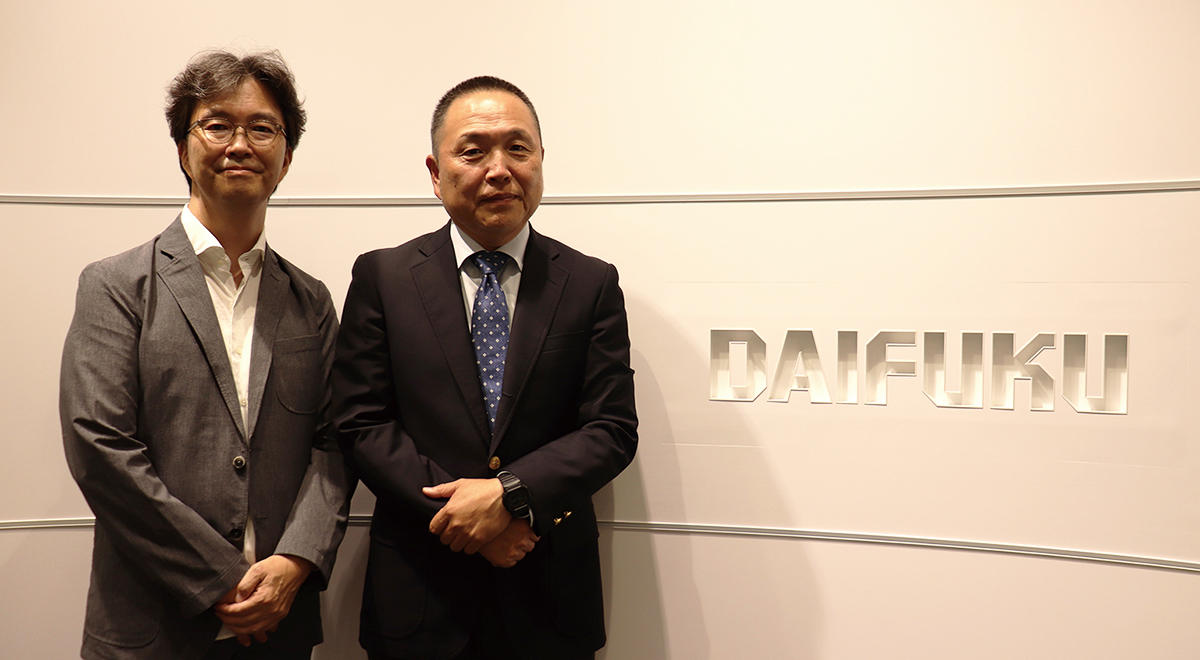
ダイフク ビジネスイノベーション本部 担当部長 松田靖氏(右)と事業構想大学院大学特任教授 電通 シニアイノベーション・ディレクター 小宮信彦氏(左)
産業界から社会全体へ
プラスチックごみ問題への挑戦
小宮 「マテリアルハンドリング」という技術の優位性で産業界の課題を解決してきたダイフクが、河川ごみ回収に挑戦するに至った背景をお聞かせください。
松田 当社は長きに渡ってモノを動かす「マテリアルハンドリング」に取り組んできました。そこから、「お客さまの困りごとの解決」を軸に、様々な事業にチャレンジしてきました。モノの保管、搬送、仕分け、ピッキング、それらを制御するシステムも含めた「マテリアルハンドリング技術」によって物流センター、半導体や自動車工場、空港など様々な産業分野で自動化、省力化などのソリューションを提供してきています。
当社は2024年5月、長期ビジョン「Driving Innovative Impact 2030」を策定しました。「未来を見据えた新たな発想での取り組みを強化し、ステークホルダーへ革新的な影響を生み出すことにより、 目指すべき経済・社会価値を実現する」という想いを込めた長期ビジョンです。
産業界だけでなく、社会の課題に対するソリューションにも注力していくという方針の中で、プラスチックごみ問題の解決を目指したプロジェクトを着想しました。
マテリアルハンドリング技術の応用
水上ロボットでごみの回収と調査
小宮 河川ごみの回収に焦点を当てた理由と、どのような技術、仕組みなのかを教えてください。
松田 海洋プラスチックごみの問題について調べる中で、全体の6~8割は陸から流れ込んできており、その中でも河川を通じて流れてくるものが多いことを知りました。にもかかわらず、流出させてしまった当事者にしか回収義務がないことから、河川のごみは放置されがちです。そこで、河川のプラスチックごみ回収に着目、水上ロボットの開発に挑戦することにしました。

水上ロボットのCGイメージ
回収するだけでなく、ごみがどこから流れてくるのかを正確に把握することが、問題の包括的な解決につながると考えています。そこで、ごみの回収に加えて調査作業も自動化しようと考えました。
全文をご覧いただくには有料プランへのご登録が必要です。
-
記事本文残り60%
月刊「事業構想」購読会員登録で
全てご覧いただくことができます。
今すぐ無料トライアルに登録しよう!
初月無料トライアル!
- 雑誌「月刊事業構想」を送料無料でお届け
- バックナンバー含む、オリジナル記事9,000本以上が読み放題
- フォーラム・セミナーなどイベントに優先的にご招待
※無料体験後は自動的に有料購読に移行します。無料期間内に解約しても解約金は発生しません。

 広告掲載のご案内
広告掲載のご案内